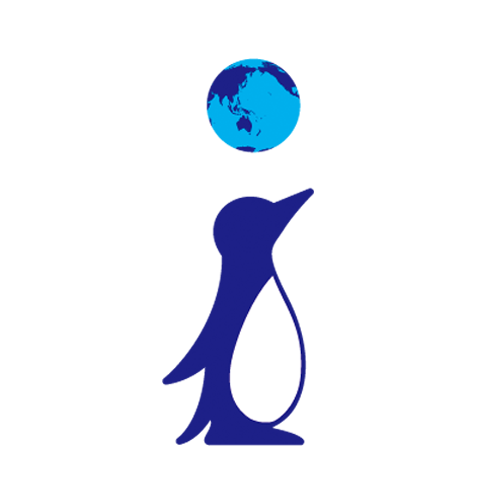事業の業種・業態によって様々な許可、登録、認定など様々な手続きがあります。
アイソシア行政書士事務所では、そういった手続きの相談から準備、書類作成や証明書収集など、申請手続きに関するお手伝いをしています。
申請を行うには、それぞれ手続きで求められる要件を把握し、人員や設備などを準備していくことになります。手続きごとに求められる要件や必要資料も異なります。要件が頻繁に変更されるものもあります。取り扱う業務や製品ごとに手続きの異なる場合もあります。いずれもすぐにはできないものばかりですので余裕をもって準備しましょう。許可後は、変更届や更新手続きの必要なものもあります。各事業様でしっかり管理しましょう。
税込500万円未満(建築一式工事の場合は、1,500万円未満)の軽微な建設工事は、許可がなくても請け負えます。それを越える工事金額の建設工事の場合は、許可が必要となります。許可申請時には、経営業務管理責任者や専任技術者の経験を証する資料や常勤性の確認のため提示する書類等多くの資料が求められます。
※ 軽微な工事の場合であっても、電気工事や解体工事など(許可ではなく)「登録」の必要なものもあります。
不特定多数の人を相手方として、不動産の売買・交換・貸借(自己物件を貸借する場合を除く)を反復又は継続して行うには、宅地建物取引業の免許が必要です。宅地建物取引士の設置が必要になります。
お酒は、店舗の小売りだけでなく、ウェブサイトなどで通信販売する際にも免許が必要です。お酒の通信販売小売業免許では、取り扱うことができる酒類が限られています。また、ウェブサイトやカタログ等、通信販売の方法(案)を明示しなければなりません。
【新規のご相談・ご依頼は受け付けておりません】医療機器は「医薬品医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(薬機法)をはじめとする法令や通知通達により規制されています。医療機器の範囲は、絆創膏やガーゼなどの簡易なものから注射針、磁気・電気治療器、コンタクトレンズ、ペースメーカーのような複雑なものまで非常に幅広く多様です。医療機器を取り扱うには、業態に応じた許可・登録だけでなく、製品ごとの届出・認証の手続きが必要となります。許可や認証の取得には要件を満たすだけでなく、業態・製品に応じて求められる体制づくりが必要となります。
【新規のご相談・ご依頼は受け付けておりません】化粧品をメーカーとして流通させたり、輸入した化粧品を日本で流通させたり、化粧品を製造するといった業をおこなうには、化粧品製造販売業許可もしくは化粧品製造業許可が必要です。取り扱う化粧品の品目ごとの届出をおこなわなければなりません。化粧品は、化粧品として販売できる成分や、表示・広告表現が定められています。いわゆる「薬用化粧品」は医薬部外品や医薬品に該当するもので、医薬部外品や医薬品として許可手続きや製品の手続きを行わなければなりません。
食品営業(飲食店の営業や食品の製造等)を営もうとする場合、食品衛生法にもとづき都道府県知事(保健所を設置する政令都市については市長)の許可を受けなければなりません。
許可申請や届出をしていないと、営業停止や罰則が適用される場合がありますので、開業するときは注意が必要です。
営利目的で、中古品を販売したり、買取りをする場合、古物商の免許が必要になります。また、売買だけでなく交換も含まれます。個人がお小遣い稼ぎ程度に自宅にあるものをメルカリで売っている分には免許はいりません。しかし、売るつもり(営利)で中古品(古物)を買い取るようなケースでは免許が必要になります。事業者(会社だけでなく個人事業者も含む)が中古品(古物)を扱う場合は古物商の免許が必要となるケースが多いでしょう。営業所を管轄する警察を通じて都道府県公安委員会に申請します。
貨物運送業
トラック(一般貨物自動車運送業)や軽自動車やバイク(貨物軽自動車運送事業)で、モノを運送する事業です。事前に許可や届け出が必要です。
旅客運送業
タクシーやバスで人を運ぶ事業(旅客自動車運送事業)です。最近ニュースで話題となる乗合タクシーなど今後の制度改正が注目される分野でもあります。人を運ぶという性質上自動車の整備や運転手に関して安全に配慮した規制があります。
旅館業/ホテル業、簡易宿所(ゲストハウス)
民泊などで騒がれたゲストハウスなどが関連する制度です。設備や衛生管理に関して規制があります。
旅行業/旅行サービス手配業
国内か海外か、ツアーの企画をするかどうかなど種類に応じて旅行業の中でも分類されます。また、乗り物や宿泊先、免税店の手配などを行ういわゆるランドオペレーターと呼ばれていた業務が、旅行サービス手配業として登録制になっています。
産業廃棄物収集・運搬業
事業者が排出した廃棄物は基本的に産業廃棄物にあたります。それぞれ規定に従って収集・運搬し、処理することが求められており、許可制となっています。積替え・保管の有無や中間処理、最終処分などがあります。弊所では、積替え・保管を含まない収集・運搬業の手続きのみ承っております。
倉庫業
他人の財産、貨物を有償で保管する業務です。施設や設備の基準が設けられ、管理者を置く必要があります。普通倉庫業の他に冷蔵倉庫業や水面倉庫業といった種類があります。
警備業
いわゆるガードマンですが、業務内容により種類があります。施設警備(1号)、雑踏・交通誘導警備(2号)、運搬警備(3号)、身辺警備(4号)があります。それぞれの業務に応じた責任者(警備員指導教育責任者)の設置が必要です。事前に営業所の管轄警察署を通じて、公安委員会の認定を受けます。